「典故300則」その103 ― 2012年12月08日 08:06
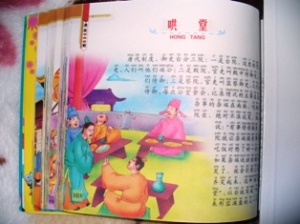
嘻嘻(にこにこ),眯眯(にやにや),嘿嘿(にたにた),哧哧(くすくす),哈哈
(げらげら),嘎嘎(きゃっきゃ)、笑い方にもいろいろあります。
典故300則その103:哄堂 hong tang
唐代の制度では官庁は三つに分けられていた。一つは台院で、ここの役人
を侍御史と言い、人々は彼らを端公と呼んだ。二つ目は殿院で、役人を殿中
侍御史と言い、人々は彼らを侍御と呼んだ。 三つ目は察院で、ここの役人を
监察御史と言い、人々は彼らを侍御と呼んだ。
毎回公堂で食べながら会合し、状況を記録する主簿は北側に座し、雑事を
主管する杂端は南側に座した。食事の時は南北に分かれて座り、固く談笑を
禁じた。食後、主簿が言った。“何か(案件が)あれば報告して下さい。”
そこで、台院は杂端に状況を報告させた。 一同は食べるのを暫く我慢して
おり、この時杂端の説明が間違ったので笑いを堪えられず、三院の人たちは
一斉に笑い出した。
この様な場面を“烘堂”と言い、以後“哄堂”と書くようになり、満座の中で一
同が大笑いすることを形容するようになった。
最近のコメント